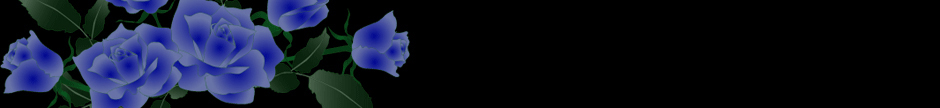今年という文字で
締めくくられる 空を
太陽が仄かな焼け跡をひきずり
金星に輝きを明け渡す頃
ポツン、ポツン、と灯る
薄明かりの外灯が
三角錐に映し出す田舎道
老いた母と年の暮れの真ん中を歩くと
海参だしの年越しそばの 臭いを纏う
高速バスの窓から見えた
振り回され 飛ばされる
風景のような年を いつのまにか
私たちは降車し
町内の明かりの優しさに
身を寄せ合える人々の束の間を
ゆっくりと歩む
昼間食べた年越しそばを
今 食べている人を思いながら
食卓にある 鯖の味噌感を開けると
今年という過去の始発が
この缶詰だけであった人々の寒さに
身を ブルッと震わせてしまう
だから、こそ、なのか、
石油ストーブのヤカンが
警笛を鳴らし終えた今
「今年」に思いを馳せる 全ての私たちが
ひと時の安らぎを求めて
深呼吸とともに
しばし一番星の夢を見ることを
来るべき未来に 手渡したい
-
最近の投稿
カテゴリー
最近のコメント
カウンター
81,006アーカイブ
- 2025年4月 (2)
- 2024年1月 (2)
- 2022年6月 (1)
- 2022年4月 (3)
- 2021年5月 (2)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (6)
- 2019年12月 (4)
- 2019年6月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (4)
- 2018年12月 (3)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (2)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (4)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (4)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (2)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (3)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (4)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (3)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (6)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (3)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (4)
- 2015年5月 (5)
- 2015年4月 (8)
- 2015年3月 (7)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (7)
- 2014年10月 (5)
- 2014年9月 (10)
- 2014年8月 (14)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (6)
- 2014年4月 (6)
- 2014年3月 (11)
- 2014年2月 (6)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (2)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (6)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (9)
- 2013年6月 (7)
- 2013年5月 (5)
- 2013年4月 (3)
- 2013年3月 (3)
- 2013年2月 (9)
- 2013年1月 (3)
- 2012年12月 (6)
- 2012年11月 (6)
- 2012年10月 (9)
- 2012年9月 (8)
- 2012年8月 (12)
- 2012年7月 (10)
- 2012年6月 (6)
- 2012年5月 (8)
- 2012年4月 (8)
- 2012年3月 (6)
- 2012年2月 (6)
- 2012年1月 (12)
- 2011年12月 (7)
- 2011年11月 (9)
- 2011年10月 (6)
- 2011年9月 (9)
- 2011年8月 (10)
- 2011年7月 (15)
- 2011年6月 (5)
- 2011年5月 (14)
- 2011年4月 (13)
- 2011年3月 (15)
- 2011年2月 (11)
- 2011年1月 (10)
- 2010年12月 (9)
- 2010年11月 (8)
- 2010年10月 (14)
- 2010年9月 (18)
- 2010年8月 (20)
- 2010年6月 (10)
- 2010年5月 (14)
- 2010年4月 (12)
- 2010年3月 (17)
- 2010年2月 (13)
- 2010年1月 (14)
- 2009年12月 (4)
- 2009年11月 (8)
- 2009年10月 (19)
- 2009年9月 (29)
- 2009年8月 (5)
- 2009年7月 (1)
- 1970年1月 (1)