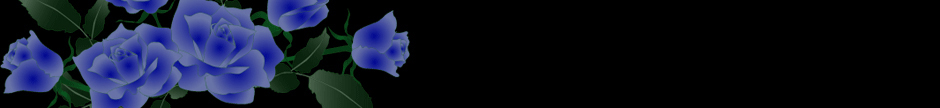手渡す人の人相が好かろうと悪かろうと
ついでにナントカ法人取締役だとか
はたまた○○財団ナントカ会長だとか
いつまでも覚えられない本人の名前と
どこまでも続く法人名・財団名・団体名
本人の名前より自己主張する予備知識が
独り歩きをどんどん始めれば
そのお墨付きを
利用する人 誉める人
たった一枚の紙切れで
年収何千万円がチラついて
握手する人 手を結ぶ人
(そして口が聞けなくなる人の
(居場所のない居場所をつくって
(押し込めたがる人
社会人なら名刺を交換するのが礼儀だろ、
と 怒鳴り散らす人の
日本人は全員社会人だろ、
と 思えば都合のいい人の
礼儀が私の指を傷つける
私は名刺を持たない
宛もない言葉だけを頼りにしている奴に
どんな社名や配置部署が似合ったあろう
選ばれた良品の上質紙たちと
有名デザイナーのレイアウト
東京4号から大阪9号の圧縮サイズの中で
生息する君たちの暗号が前進して
ちいさな草花を踏みつけて行く
酔っぱらった社会人の
スマホで作れるお手軽保障
その紙切れの上で
人が浮いたり 沈んだり
-
最近の投稿
カテゴリー
最近のコメント
カウンター
75,137アーカイブ
- 2024年1月 (2)
- 2022年6月 (1)
- 2022年4月 (3)
- 2021年5月 (2)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (6)
- 2019年12月 (4)
- 2019年6月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (4)
- 2018年12月 (3)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (2)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (4)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (4)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (2)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (3)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (4)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (3)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (6)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (3)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (4)
- 2015年5月 (5)
- 2015年4月 (8)
- 2015年3月 (7)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (7)
- 2014年10月 (5)
- 2014年9月 (10)
- 2014年8月 (14)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (6)
- 2014年4月 (6)
- 2014年3月 (11)
- 2014年2月 (6)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (2)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (6)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (9)
- 2013年6月 (7)
- 2013年5月 (5)
- 2013年4月 (3)
- 2013年3月 (3)
- 2013年2月 (9)
- 2013年1月 (3)
- 2012年12月 (6)
- 2012年11月 (6)
- 2012年10月 (9)
- 2012年9月 (8)
- 2012年8月 (12)
- 2012年7月 (10)
- 2012年6月 (6)
- 2012年5月 (8)
- 2012年4月 (8)
- 2012年3月 (6)
- 2012年2月 (6)
- 2012年1月 (12)
- 2011年12月 (7)
- 2011年11月 (9)
- 2011年10月 (6)
- 2011年9月 (9)
- 2011年8月 (10)
- 2011年7月 (15)
- 2011年6月 (5)
- 2011年5月 (14)
- 2011年4月 (13)
- 2011年3月 (15)
- 2011年2月 (11)
- 2011年1月 (10)
- 2010年12月 (9)
- 2010年11月 (8)
- 2010年10月 (14)
- 2010年9月 (18)
- 2010年8月 (20)
- 2010年6月 (10)
- 2010年5月 (14)
- 2010年4月 (12)
- 2010年3月 (17)
- 2010年2月 (13)
- 2010年1月 (14)
- 2009年12月 (4)
- 2009年11月 (8)
- 2009年10月 (19)
- 2009年9月 (29)
- 2009年8月 (5)
- 2009年7月 (1)
- 1970年1月 (1)